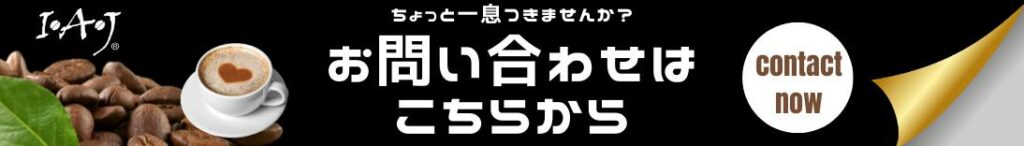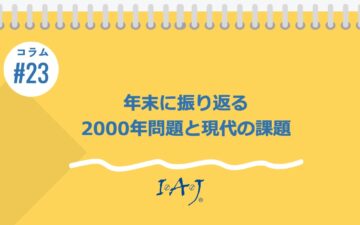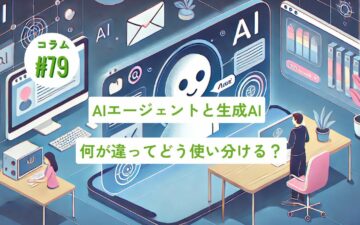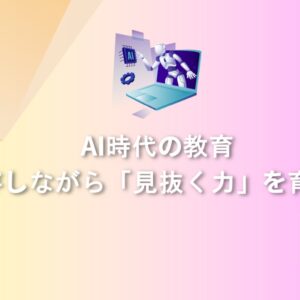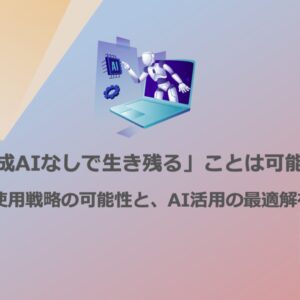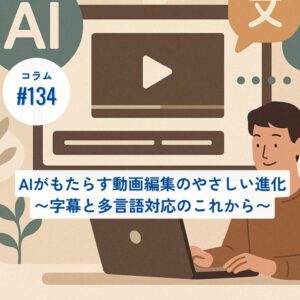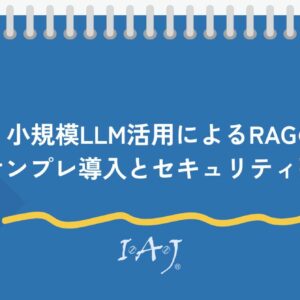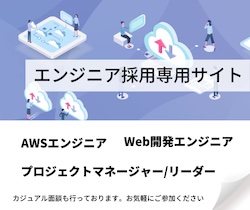1. 情報が「そこにある」だけでは、使いこなせません
業務を進めるうえで、過去の資料や知見に頼る場面は少なくありません。けれど、いざ探そうとすると見つからない、誰が最後に更新したのか分からない、そんな経験をしたことはありませんか?私自身、何度も「これ、どこにしまってたっけ…」と画面の前で手を止めたことがあります。情報はあっても、探す時間がかかってしまえば、ナレッジとは言えませんよね。
2. AIが、情報の地図を描いてくれる
最近では、AIを活用して社内ドキュメントを整理しやすくする取り組みが増えてきました。たとえば自然言語処理を活用した検索機能なら、「〇〇の手順書ってどこ?」と入力するだけで、関連するドキュメントを一覧にしてくれます。こうした機能によって、私たちは「どこにあるのか」を意識せずに、必要な情報にたどり着けるようになるのです。ちょうど、迷子にならない地図をAIが描いてくれているような感覚ですね。
3. ナレッジは、共有されて初めて価値になる
もう一つ大事なのは、「ナレッジを活用できるかどうか」です。個人にとどまってしまっては、どれほどの知見も組織の力にはなりません。最近は、社内チャットや議事録、メールなどを横断して知識を可視化するツールも登場しています。誰かが発したひとことが、思わぬプロジェクトで役に立つかもしれません。ナレッジを「場」に閉じ込めず、「全体で使える知恵」として整えていくことが、AIと人の協働における鍵だと感じます。
4. 小さな一歩が、組織の知恵を育てる
大がかりな仕組みを一気に導入しようとすると、どうしてもハードルが高く感じられます。でも、最初の一歩は小さくても構いません。たとえば「よく使うフォーマットをAIが分類してくれるようにする」「引き継ぎ資料をAIに要約させてみる」など、小さな業務改善から始めてみてはいかがでしょうか。試行錯誤を積み重ねるうちに、ドキュメント整理やナレッジ活用の土台が、自然とできていくはずです。
AIは単なる効率化ツールではなく、組織の知恵を“活かす”ためのパートナーです。情報が生きてこそ、私たちの仕事ももっと豊かに、心地よいものになると信じています。

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?