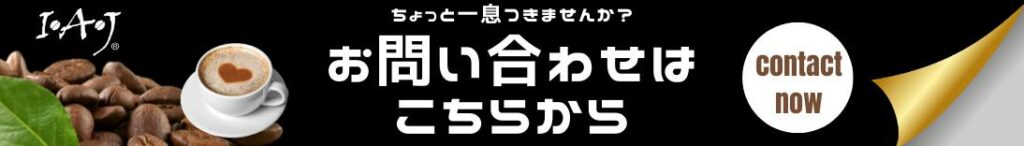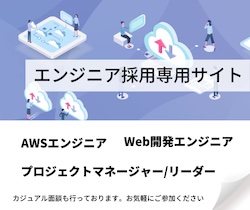1. 一つになったテクノロジーの力
GoogleがFitbitを買収したとき、「健康管理の未来が変わるかもしれない」と思った方も多いのではないでしょうか。私もそのひとりです。GoogleのAIとクラウド技術、そしてFitbitのウェアラブル技術。この二つの融合は、まさに”テクノロジーとヘルスケアのクロスオーバー”と呼ぶにふさわしいインパクトがありました。
Googleが得意とするのは、膨大なデータを解析し、個々人に最適化されたフィードバックを返すこと。一方、Fitbitは心拍数・睡眠・活動量といった日々の健康指標を、高い精度で取得する技術を長年にわたって磨いてきました。この二つが手を組んだことで、ただの「記録装置」だったウェアラブルが、「健康を導くアドバイザー」へと進化しつつあるんです。
2. ユーザーに寄り添うAIの進化
Google Fitや新しいFitbitアプリでは、ユーザーの生活習慣に合わせたアドバイスがAIによって提案されるようになってきました。例えば、「昨日より睡眠の質が低下しています。今日は30分早めに寝てみませんか?」といった、さりげない提案が通知されるんです。
私はシステムエンジニアとして日々PCの前で過ごすことが多いんですけど、Fitbitの「座りすぎですよ」通知に、何度助けられたことか…。GoogleのAIがバックで動いていると考えると、ちょっとだけ背筋が伸びます(笑)。
これって、ただ便利ってだけじゃなくて、私たちのライフスタイルそのものを見直す”きっかけ”をくれる技術なんですよね。そこが、ただのハードウェアとの違いだと思います。
3. 技術に“温かみ”を感じる瞬間
最近のFitbitデバイスって、ただ情報を出すんじゃなくて「あなたのことをちゃんと見てるよ」って感じるんです。心拍数やストレスレベルの測定はもちろん、気分の記録やマインドフルネスの提案など、心の健康にもアプローチしてくれるのがうれしいところ。
Googleの技術が加わったことで、アプリのUI/UXもぐんと洗練されました。個人的には、Vue.jsやFlutterであのスムーズな動きがどう構成されてるのか気になっちゃうんですけど、それは職業病ですね(笑)。
でも、技術って冷たく見られがちだけど、こうして人の心に寄り添う形で進化していくのを見ると、本当にワクワクします。
4. これからへの期待
今後は、FitbitデバイスがGoogle PixelやAndroidのシステムともっと深く連携するようになるはずです。ヘルスデータが一元管理されて、健康診断のデータや病歴、日々の行動データなどがすべてつながったら…。たとえば、「体調が崩れそうだから明日の予定を少しゆるくしましょう」なんて提案が出る未来もありえますよね。
プライバシー保護の議論は欠かせませんが、それでも私はこの進化に期待したいと思います。健康って、当たり前にあるようで、気づいたときには崩れているものだからこそ。テクノロジーが日常の“予防”にまで寄り添えるって、本当に心強いです。
GoogleとFitbitの技術が出会ったことで、私たちの健康管理は「自己管理」から「伴走型」へと変わりつつあります。テクノロジーがどんどんパーソナルに、優しく、そして賢く進化していく様子に、私は大きな期待を寄せています。これからも、「技術の進化=人の幸せ」に近づいてくれると信じて、日々の暮らしにワクワクしていたいですね。

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?