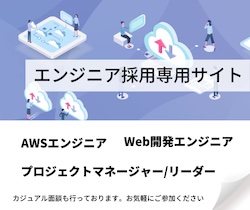「業務効率化」の先にある問い
AIや自動化技術が、業務の効率を高めるための“武器”として注目されて久しい時代。
私たちIT企業も、日々クライアント企業の業務改善やコスト削減に関わる開発をお手伝いしています。その中で最近、ふと思うことがあります。
「業務効率化した結果、社員は充実感を得られているのでしょうか?」
見かける結果は、時間の削減、それによる生産性の向上や人件費の削減が大半です。
業務効率化によって生まれた時間を、その分より多くの仕事に費やし、生産性を高めることは、もちろん企業にとって非常に重要な取り組みです。
しかし、その効率化が進んだ先で、社員の「心のゆとり」や「充実感」も同時に考えられれば、さらに一歩進んだ成果が得られるのではないでしょうか?
どういうことか、この後ご一緒に見てゆきましょう。
この記事では、
・業務効率化の先にある社員の充実感とその重要性が、企業の成長や事業の持続可能性にどのように繋がるか
・福利厚生を効果的に活用するためのシステム開発のアプローチ
・自社開発システムが持つ柔軟性と企業特有のニーズへの対応
について掘り下げていきます。ぜひ最後までご確認くださいね。
【自社開発サポート】IAJにおまかせ!こちらからお気軽にお問合せください >>
・企業内でのシステム開発やデジタル化を推進している方
・企業の成長や従業員のエンゲージメント向上に関心がある方
・業務効率化をすでに行なっており、さらなる企業向上を目指す方
業務効率化は第一歩。次に目指す先とは?
業務効率化の先に見えるのは、単なる「時間の節約」や「コスト削減」だけではありません。
むしろ、その先である、業務をこなしてくれている社員一人ひとりの「人生の充実」をサポートするための仕組みづくりが、今後の企業の成長に繋がるのではないかと思います。
なぜなら、企業全体の活力やエンゲージメントは一人一人の従業員の労力で成り立っているからです。
その労力は、その社員のモチベーションやエンゲージメントに大きく影響しますよね。
つまり、「社員が生み出した時間をどのように使うか」ということも大事なのではないでしょうか。
例えば、効率化によって生まれた余暇時間を仕事にすべて充てるのではなく、その時間を自己成長やプライベートの充実に使えるようにサポートすることでも、社員の充実感は変わってきそうですね。
個々の充実感が高まれば、企業としてもさらに良くなって行けるはずです。
心にゆとりがあるからこそ、新しいアイデアが生まれたり、前向きにチャレンジできる部分もありますよね。そうした“人の力”こそが、長期的な生産性の土台となると思います。
社員の幸福度やウェルビーイングに関しては既に多くの企業が注力しており、その重要性は確立されていますね。
業務効率化を進める今、ここに立ち返る意義があるのではないかなと考えます。
つまり、これからの企業経営においては、業務効率化だけではなく、社員の心の充実を支える仕組みづくりをすることで、さらなる向上が期待できるのではないでしょうか。
働く人の心に寄り添う仕組みづくり
社員の心の充実の重要性
ワークライフバランスの促進、従業員満足度やリスキリングなどによるモチベーションの向上や、従業員のウェルビーイング改善による欠勤率の低下などが、会社全体に良い影響を与えるということは、すでに多くの実例からも明らかです。
ここでは詳細については省きますが、興味のある方は外部記事を参照していただければと思います。
サッポログループの健康経営
サッポログループでは「健幸創造宣言」を策定し、従業員の心身の健康増進に取り組んでいます。施策として、定期健康診断の受診促進や産業医・保健師による面談を実施し、健康意識の向上を図っています。これらの取り組みにより、喫煙率の低下や睡眠の質の向上、運動習慣者の増加などの成果が報告されています。
参照元:成長と生産性向上に向けた人的資本投資
サイボウズ株式会社
自由な働き方を推進するため、9パターンのワークスタイルを導入し、社員が自分で働き方を選択できる仕組みを整備。また、「育自分休暇制度」を導入し、自己成長を目的とした転職や留学を支援した結果、離職率が28%から5%弱に改善。社員が自己成長を実感できる環境づくりが定着率向上に寄与しました。
参照元:働き方を改革して企業を成長させる施策
個人の充実は確かに自己実現の一環であるという意見もありますが、あえて社員には会社から提供される福利厚生を利用してもらう意義があると私は考えています。
会社からのサポートを受けることで、たとえ潜在的にでも、社員は「ギブアンドテイク」の精神で貢献しようという意欲を持ちやすくなると思います。
業務改善だけでは語りきれない、“社員のその先”を見据える視点が、これからの企業価値を大きく左右するかもしれません。
しかし、実際には━━
- 制度があっても使いづらい
- 情報が分かりづらくて埋もれている
- 活用したくてもタイミングを逃す
というように、”使われない福利厚生”が多く存在するのも事実です。
福利厚生 × システム開発でエンゲージメント向上!5つのポイント
福利厚生制度が提供されていても、社員がそれを「使いたくなる」と感じなければ、実際にはその効果を十分に発揮できません。
そこで重要なのが、福利厚生を使いやすくする・使いたくなる仕組みを作ることではないでしょうか。システム開発を活用することで、社員がより簡単に福利厚生を利用できる環境を整えることができます。
「システムで管理してるよ」と思われる方もいるかもしれません。
ですが、ここで私が思うのは、シンプルで良いのですが、「経費を抑えるあまり、使いにくいシステムになっていないか」や「少しでも“使いたくなる”仕様を入れてみるのはどうかな」というところです。
使い勝手が悪くて福利厚生が利用されず期待した効果が得られないようでは、せっかくの福利厚生も無いに等しくなります。もったいないですよね。
ではどうすれば良いのか考えてみましょう。
① すべての福利厚生を一元管理する
意外と多いのは、福利厚生についてバラバラに管理されていることです。
たとえば、健康診断やジムの割引、休暇制度、教育支援などが別々のアプリやポータルで管理されていると、社員はどこで何を確認すべきか分からなくなってしまいますよね。
このような場合、社員は必要な福利厚生を簡単に見つけられず、利用しづらいと感じてしまう恐れがあります。
すべての福利厚生を1つのプラットフォームで管理することで、社員が簡単にアクセスできるようにしておくのが良いでしょう。
② 直感的なユーザーインターフェース
また、費用を抑えるあまりユーザーインターフェース(UI)がわかりづらく、利用する社員が操作に時間をかけてしまうことがあります。
また、福利厚生制度が多いのは魅力的ですが、そこが整理されていなければ、利用手続きが煩雑だったり、申請方法がわかりにくかったりすることがあります。
上記2点について、
説明書を読まずに始められるような直感的な操作を好む現代において、強制力のないものに対して「使用方法を理解・把握すること」から始めるには、ハードルが高く感じられそうです。
そうしたわかりづらさは、従業員が積極的に利用しなくなる原因になってしまいます。
特に、忙しい社員にとっては、手間をかけずに利用できることが大切だと思います。
③ その他機能
福利厚生アプリが提供する制度の利用期限や新しい特典の通知が不十分だと、社員は制度を活用するタイミングを逃すことがあります。例えば、福利厚生の期限が近づいていることや、新たな福利厚生が追加されたことを社員に適切に伝えないと、社員は「使い忘れ」に繋がり、最終的に福利厚生が活用されないことになります。
④ AIを活用し、パーソナライズした福利厚生を提案する仕組み
福利厚生はすべての社員に一律に提供されるものですが、社員一人ひとりのライフステージやニーズは異なります。
例えば、役職、若手社員と中堅社員、既婚者と独身者、または親の介護をしている社員など、それぞれの状況によって最適なサポート内容は異なりますよね。
そこにAIを活用した社内ポータルを作成し、社員一人ひとりのプロフィールや過去の利用履歴、個々のライフイベント(例えば、結婚、出産、転居など)を基に最適な福利厚生を提案できるような仕組みを作るのはいかがでしょうか。
具体的には、以下のような提案が考えられます。
これにより、社員は自分に最も合った福利厚生をスムーズに見つけ、利用しやすくなります。
また、企業側にとっても、社員がどの制度を利用しているか、どの福利厚生に関心があるかをデータとして収集でき、より最適な制度運用もできることでしょう。
⑤ 社員同士の交流を深めるような社内SNSやイベント募集ツール
福利厚生は、単に物理的な支援や金銭的な支援にとどまらず、社員同士の関係を強化するためにも重要です。
特にリモートワークやフレックスタイム制の普及により、社員同士の顔を合わせる機会が減っている現代では、社内コミュニケーションの活性化が求められています。
社内SNSやイベントマッチングツールを導入することで、社員間のつながりを強化し、プライベートの充実や人間関係を支援することができるでしょう。
これらのツールを活用することで、社員同士のつながりが強化され、より良い職場環境が生まれるとともに、社員の仕事以外の充実感が向上します。
このような交流が社員の仕事への満足度を高め、企業全体のエンゲージメント向上にも繋がるのです。
これらの仕組みがあれば、福利厚生の活用がより身近になり、より効果的なものになりそうですね。
自社開発のメリットとは?—既存アプリとどう違うのか?
福利厚生に関しては、既存のアプリも多数あります。
それらは一般的な機能を提供しているため、特にこだわりを持たなかったり、何が良いかわからない企業には便利だと思います。費用も一からスクラッチで開発するよりも抑えられる可能性が高いです。
一方で、独自のニーズや企業文化にフィットさせたいという考えをお持ちでしたら、ニーズを満たすにはやや不十分かもしれません。
特に、特定の業界に特化した福利厚生制度や、会社独自のプライバシー規制に対応する必要がある場合、既存のアプリでは柔軟性に欠けることもあります。
以下に、自社開発ならではの主な利点を紹介します。
人生をちょっと豊かにする仕組みを、一緒につくりませんか?
業務効率化はあくまで第一歩。
その先にある、社員一人ひとりの「人生の充実」を支える仕組みを作ることが、企業として成長するためにも、事業を継承していくためにも次に目指すべき方向ではないでしょうか。
効率化によって生まれた時間を、どう価値あるものに変えていけるのか。
その答えを、一緒に考えてみませんか?
━━というところで、最後に創業20年、多くのスクラッチ開発を行ってきた当社IAJについて紹介させてください。
IAJに頼みたい!ここがポイント
運用保守については「社内のシステム部門で行うので、不要」とされる企業様もいらっしゃり、各企業様によってサポートの度合いや内容が変わってきます。そのため、システム開発と別途お見積もりの上でのご契約となりますので、その後の運用面についても不安な点がございましたら、まずはご相談くださいね。
よくある質問と回答
- 受託開発を依頼する際、どのような要件定義を準備すればよいですか?
-
要件定義をしっかり行うことは、受託開発の成功に欠かせません。私たちは、お客様と密にコミュニケーションをとり、企業特有のニーズや目的を深く理解した上で、要件定義を進めます。明確な目標設定と、仕様書の作成をサポートし、開発後のスムーズな運用を見据えた最適なシステム設計を提供します。
- 開発プロセスにおいて、どのように進捗管理を行っていますか?
-
私たちは、お客様と共に開発の進捗を透明に管理するため、定期的なレビューや進捗報告を実施しています。タスク管理ツールを使用し、スケジュールの遅延や変更にも迅速に対応できる体制を整えています。進捗状況を共有し、柔軟に対応することで、納期遅れや仕様変更にも安心して対応できます。
- 業務システムを自社開発する際のメリットは何ですか?
-
開発後の運用・保守は、要・不要が分かれるため別途ご契約の上、サポートさせていただいております。要件定義や開発が始まる前に、どこまでのサポートをご希望されるかお伺いいたしますので、ご希望をお申し付けください。お客様のご要望に応じた形でのサポートを検討させていただき、別途お見積もりさせていただきます。
多いのは、システム導入後の運用に関する疑問や問題が発生した際に、専任サポートチームが迅速に対応できるよう、ご指定の人月分の人員を確保しておくような形です。その他定期的なメンテナンスやアップデートに関してなどもご要望であれば、ご契約の際にご相談ください。 - システム開発後のセキュリティ対策はどうなりますか?
-
私たちは、システム開発時にセキュリティ対策を重要視しています。最新のセキュリティ技術を導入し、データの暗号化やアクセス権限の管理を徹底します。また、開発後も定期的なセキュリティチェックを行い、システムの脆弱性を早期に発見し、迅速に対策を講じます。企業の情報資産を守るための万全の体制を提供します。
他にも質問があればお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせフォーム】その他、ご質問はこちらから>>
まとめ:業務効率化だけじゃない。社員の充実感に寄り添うシステム開発
では、この記事の重要ポイントを確認してゆきましょう!
ご確認いただき、ありがとうございます。
当社にご相談いただいた際には、あなたの会社に合った福利厚生システムを一緒に作り、社員の心の充実をサポートするお手伝いができればと思います。
今回は以上になります。改めて最後までご覧いただきありがとうございました!

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?