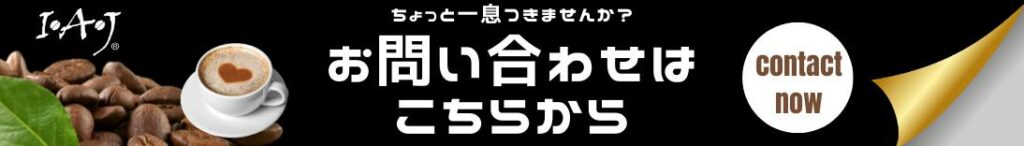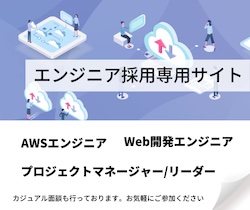1. 空間に溶け込むUIデザインの力
スマートグラスにとって、UI設計の命は「見え方」と「触れ方」の調和です。表示情報が視界に固定され、頭を動かしても追従するように設計されることで、現実との一体感が生まれます。例えば、XReal Air 2 Ultraでは仮想スクリーンが空間に固定され、ユーザーの頭の動きには連動しない設計が施され、高い没入感と安定感を実現しています
こうした空間に溶け込むUIは、利用者が「視線をそらす」間もなく情報を得られる未来の自然な体験へと昇華します。
2. マルチモーダルなインタラクション:自然操作の追求
スマートグラスのUIは、タッチ・音声・視線・ジェスチャーといった多様な操作を融合させることで、直感的かつ柔軟な体験を生み出します。たとえば、Rokid AR Spatialでは視線や音声制御といった自然なインターフェースを備え、軽量化と視覚的・操作的な快適性を両立しています。
さらに、空間インタラクションの未来には、状況や周囲環境に適応するUIも期待されています。アプリがユーザー周辺の物体や人を認識し、最適なインターフェース配置を自動的に調整する「SituationAdapt」のような研究も進んでいます。これは、画面が物理環境に干渉せず、人とのやりとりも邪魔しない柔軟なUIを生む可能性があります。
3. 空間インタラクションがもたらす応用の広がり
空間インタラクションを起点にしたスマートグラスは、ガイドやエンタメだけでなく、認知支援やウェルネスといった分野にも展開が進んでいます。例えば、NavMarkARという高齢者向けのナビシステムでは、ランドマークベースのAR案内により、室内でも位置の把握や経路理解が向上したという成果が出ています。
また、Visuo‑haptic混合現実では、視覚だけでなく触覚も統合した体験により、仮想オブジェクトの操作に対して現実世界のような感覚をもたらす研究も進行中です。見て、触れる体験が同時に発生することで、空間インタラクションの自然さと説得力がより強化されます。
さらに、最近のスマートグラス市場では、Meta×Ray‑BanやSnapやAndroid XRプラットフォームなど、軽量なデザインとAI対応のバーチャル要素を組み合わせたデバイスが増えており、空間インタラクションの普及が現実のものになりつつあります。
スマートグラスのUI設計と空間インタラクションは、新たな情報体験を創り出す革新的な舞台です。視線やジェスチャー、音声といった自然な操作と、状況に応じて変化するインターフェース、さらには視覚と触覚の統合によって、デジタルとリアルがシームレスに融合します。こうした進化は、単なる技術の延長ではなく、私たちの生活そのものをもっと豊かに、もっと直感的に変えてくれるでしょう。

<<IAJってどんな会社?>>
創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。
おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。
私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。
他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?